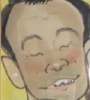小仏城山について
標高670mの小仏城山は、北条氏の武田氏に対する防塁があった場所だといわれており「じょうやま」、「しろやま」とも呼ばれている。
小仏城山に到着して、一休みにした。この小仏城山には2件のお茶屋さんが長年にわたり営業されており登山者に飲食物や休憩するためのベンチとテーブルを提供してもらっている。自分はここでよく「なめこ汁」を頂くのだが、城山茶屋さんでは、「なめこ汁」は醤油仕立てのお味で、かたや春美茶屋さんでは、味噌仕立てのお味。
城山茶屋さんの、なめこ汁 春美茶屋さんの、なめこ汁


「小仏城山」に立ち寄られる機会のある方はそれぞれ食べ比べてみるのも一興かと思う。ちなみにかみさんは、春美茶屋さんの味噌仕立てのなめこ汁を食した。この日は、日差しが強く、平坦な道を歩いているだけでも、体温が上昇して来るのが分かり、汗をかいて塩分も体の外に出てしまうので、なめ汁は、 「熱中症予防」にもなった。いつもであれば、なめこ汁ほかに、あわあわが欲しいところであったが、ここはぐっとこらえる。しばしの休憩ののち、次の目的地小仏峠に向かう。途中の、小仏城山巻き道は今だ通行止めのようだ。2019年11月10日の時はトラロープが張られて通行止めになっていたが、その後訪れた時はトラロープが下にだらんと垂れ下がり跨いでいけば通行できるのかと思っていたがこの通行止めの注意板は残っていたので、右側の木段道を進んだ記憶がある

そして 現在では、丸太フェンスが設置されていた。上にも書いたが、面白半分のハイカーが注意書きを無視してこの道を通過する事が多くこのようなフェンスを設置したと思われる。道の状況が写真入りであるにも拘らずその道を歩くことが理解できなし、もし万一怪我をした時に、レスキューの方々が救助に向かう時の事を考えるとなんともいない気持ちになる。

通行止めになっていない巻道を使い、狸さんの置物のある小仏峠に到着。昔から疑問なのだがなぜ小仏峠に狸の置物があるのか分からない。

この裏手が、景信山への取り付きなのだが、ここから景信山への急坂が奥高尾縦走の難所の一つだと思う。現に、このあたりからかみさんの足がぴたりと止まり始めた。おそらくここを大苦戦せずに景信山まで到着すれば、奥高尾縦走の可能性はかなり高くなるのではないだろうか

ひと登りすると、ゆるい尾根道に変わる。このあたりから山頂までは、伐採によって明るく開けた周りの景色を愉しめる道に変わるが、日差しが容赦なく照り付けて汗が噴き出てくる。

さらに歩いて行くと、下に記した分岐が出て来る。

残念ながら右側の南東尾根・ヤゴ沢コース方面へと続く道は通行止めだった

景信山へと続く道は、急坂になるのでかみさんは立休みを入れながら歩いてきた。

右側の幟ではないのだが、景信山にいらっしゃいませ~お疲れ様~。
疲労困憊で登ってきたかみさんに、高尾山から小仏城山へと続く稜線をみながらあそこから歩いてきたんだよと説明したのだが果たして耳に残っていたかどうかはわからない。それほどへとへとだったと言うことだろう。

ここから一段上にあるかげ信小屋に向かいここで休憩にした。休憩前に1枚

テーブルに腰かけて、45分ほど休憩し、もう少し先に行ってみると?聞くと今日はこの辺でと弱気な言葉が出てきたのでここから、小仏バス停に下ることにした。

この下りは、バスの時間により登ってくるハイカーが多い時間帯と少ない時間帯がある。単調な下りが続き

登山口に到着

あとは、バスの到着する時間を計算しながらバス停に向かった。

この日のおさらい
行 程(休憩時間を含んだ到着時間)